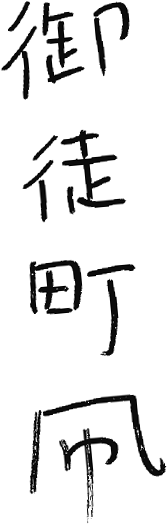欠伸のような吐息が
どこまでもということに
飲み込まれていく
それでも服を着て
肌触りだけを頼りに
歩みを進める
後頭部の鈍い
クラクションに急かされて
足場さえなくなる
光の届かない
そこでは
すべてに自由が与えられた
知らぬ間に離れていった
己という影
横になった砂時計の淵に
腰を下ろして
見つめ合う
固くなったパンを分け合って
人間の言葉で合図を送る
小鳥の囀りよりもさやかに