

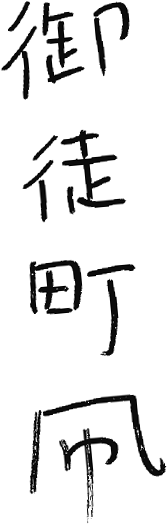

二〇〇九年一〇月一四日(水)
どうして詩を書くのかと問われたらなんて答えたらいいのだろうかとセルマネロは部屋の床に寝転がり考えていた。
セルマネロは詩を書いていることを公言していなかったから、この問いはもはや自分から自分への問いに近いものだった。
学校に行くようになってから、セルマネロは詩を書き留めるということを始めたのだったが、詩のようなものを心の中で構築することは言語を習得することと同くして行っていたのだった。
だから、学校に行くということがセルマネロを詩に向かわせたのではなく、教室という空間の緩い拘束が、ただ書くという行為を促しただけで、学校と詩の相関性はほとんどないと言ってしまっていいことではあったが、書かれた詩を視覚的に認識することと書くという単純な運動がセルマネロになんらかの変化を与えたことは事実ではあった。
セルマネロは詩というものを理解していなかった。
詩を書くということが、セルマネロにとって自然なことであったため、改めて考える機会がほとんどなかったのだ。
書かれた詩を、後になって見返したとき、どうしてこんな詩を書いたんだろうと自省することはしばしばあったが、その行為はトイレで自分の排泄物を流し去る前に、瞬間眺めてしまう時となんら変わりのない無意味なことだった。
ニックタックは帰宅すると父親のポンヴェニックに付いて市場へ行くのが、毎日の習慣だった。
ポンヴェニックは自宅でリストランを営んでいて、日替わりのオードブルの食材を市場で仕入れているのだった。
ニックタックは市場の喧噪を好んでいた。
採れたてのベジーやフィッシュの匂いはニックタックの好奇心を無尽蔵に刺激したし、なによりも市場に訪れる人たちの活気がニックタックの性分に合っていたのだった。
道すがらニックタックはポンヴェニックに訊いた「今日は何をメインにするの?」
ポンヴェニックは早足を緩めることなく答えた「まだ決めてない」
「そっか、じゃあ、オレが決めてもいい?」とニックタックは返した。
「それはダメだ」とポンヴェニック。
「どうして?」とニックタック。
「オレの店だから」とポンヴェニック。
この時だけ、ポンヴェニックは振り返り、ニックタックの表情をうかがった。しかし、ニックタックは暮れる夕焼けに視線を奪われていて、その瞬間に二人の視線が合わさることは永遠になかった。
「それもそうだねー」と、気のない返事をしたニックタックは、今日学校であったことを思い返してた。
そして、アフターランチの運動の時に、パトムに言われた何かが気に触ったことが蘇ったのだけれど、それが具体的に何だったのかを思い出せず、根っこの不安定な不愉快に胸のあたりをモヤモヤとくすぐられているような感じになり、少しだけ内股で歩いてしまっていたが、ニックタックにその自覚はなかった。
しばらく二人は無言で歩いていた。沈黙は不均衡な足音に消されていた。
ポンヴェニックは誰にともなく「涼しくなったな」と言った。
それは誰にも聞かれることのない、純粋なつぶやきだった。
二〇〇九年一〇月一四日(水)
