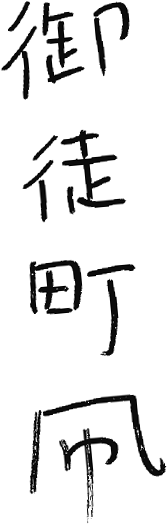布団の中へ滑り込むように、いや、本当に滑り込んだのかもしれない。と、セルマネロは思った。
布団は部屋の沈黙を吸い込み、ひんやりとセルマネロの体を包み込んだ。
布団はセルマネロの体温と同調するかのように、少しずつその温度を上げる。
布団の中で、セルマネロは目を閉じていた。
暗闇がまぶたの裏から溢れだし、夜空の星々を一つずつ塗りつぶしてゆく。
そんなイメージがセルマネロの枕元でクルクルしていた。
窓の外に風が吹いているのが分かる。
カタカタと震える窓は、懐かしい話を語りかけてくる古い友人だった。
眠りは、どの辺まで来ていたのだろう。
木のボートに乗って、眠りは来ていた。
あてもなく漂うボートは、月の光に導かれていった。
セルマネロは眠りの中で、笑い声を聞いた。
それは限りなく音楽に近かった。
音楽が止まない夜、テーブルの上の血の跡が月明りに輝く。
セルマネロが今よリずっと幼かった頃に、工作用の削りナイフで誤って手の平を傷つけた時に流れた血が作ったテーブルの跡。
怒られることが嫌で、セルマネロは泣くこともせずに、血をテーブルに擦り付けていた。
その夜も、大きな月が空に昇っていた。
それは間違いのないことだった。