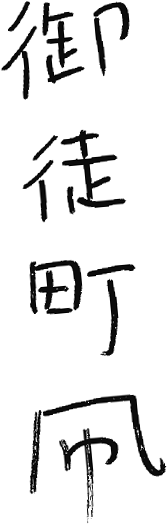セルマネロは星空を眺めながら
セルマネロは星空を眺めながら、宇宙の始まりについて考えを巡らせていた。
広がり続けると言われている宇宙のその先にいったいなにがあるのかと。
宇宙とは想像力の限界のことだと、図書館にある本に書かれていたことがセルマネロの心にずっと残っていて、宇宙を眺めながらその言葉を直接思い出したわけではなかったけど、セルマネロは自分の想像力を遥か頭上の世界へと柔らかくリリースしていた。
宇宙は明るかった。
星々の輝きさえ霞むほど宇宙それ自体がほんのり発光しているかのようだった。
そして宇宙を覆う闇は段階に分かれていて性質の違う存在を誇示しているのだった。
セルマネロは宇宙を眺めながら、様々な物語を紡いでいた。
一つとして同じ物語はなく、しかし、すべての物語がお互いに影響を与えながら流れているのだった。
セルマネロの頬を涙が伝う。
涙が薄く湿った唇に触れたとき、セルマネロは味覚から自分が泣いていることに気付くのだった。
と同時に家族のことを思う。
セルマネロは白鳥の背中に乗って、夕焼けを目指してる旅人の孤独のようなものをなぜか心に留めているのだった。
二〇一〇年〇一月一二日(火)
セルマネロは星空を眺めながら
セルマネロは星空を眺めながら、宇宙の始まりについて考えを巡らせていた。
広がり続けると言われている宇宙のその先にいったいなにがあるのかと。
宇宙とは想像力の限界のことだと、図書館にある本に書かれていたことがセルマネロの心にずっと残っていて、宇宙を眺めながらその言葉を直接思い出したわけではなかったけど、セルマネロは自分の想像力を遥か頭上の世界へと柔らかくリリースしていた。
宇宙は明るかった。
星々の輝きさえ霞むほど宇宙それ自体がほんのり発光しているかのようだった。
そして宇宙を覆う闇は段階に分かれていて性質の違う存在を誇示しているのだった。
セルマネロは宇宙を眺めながら、様々な物語を紡いでいた。
一つとして同じ物語はなく、しかし、すべての物語がお互いに影響を与えながら流れているのだった。
セルマネロの頬を涙が伝う。
涙が薄く湿った唇に触れたとき、セルマネロは味覚から自分が泣いていることに気付くのだった。
と同時に家族のことを思う。
セルマネロは白鳥の背中に乗って、夕焼けを目指してる旅人の孤独のようなものをなぜか心に留めているのだった。
二〇一〇年〇一月一二日(火)