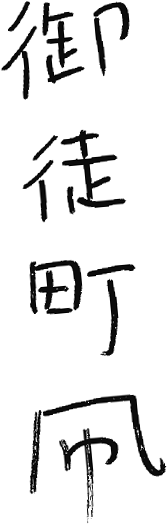雨に濡れる
早く起きた娘を抱いて
クロワッサンを買いに家を出たら
思っていたよりも帰宅が遅くなり
妻はもう出かけていた
パンを食べたり午前中を過ごしていると
妻から電話があり曜日を間違えたと言い
慌ただしく帰ってきた妻は雨に濡れていた
早く起きた娘はお昼頃にまた眠るので
それまでの時間私は娘と遊んでいた
一歳の娘と間もなく四十になる私とでは
時間の密度は違えども
今日はどちらにとっても
やがて忘れられる一日なのだろう
と言い聞かせるように私はそこにいる
せめてと娘の姿を焼きつけようとするが
そのことさえも日常の中に紛れ込んでしまう
雨に濡れた妻が
その時なにをしていたのかさえ
もうこの詩の中に存在していない
二〇一六年一〇月一〇日(月)
雨に濡れる
早く起きた娘を抱いて
クロワッサンを買いに家を出たら
思っていたよりも帰宅が遅くなり
妻はもう出かけていた
パンを食べたり午前中を過ごしていると
妻から電話があり曜日を間違えたと言い
慌ただしく帰ってきた妻は雨に濡れていた
早く起きた娘はお昼頃にまた眠るので
それまでの時間私は娘と遊んでいた
一歳の娘と間もなく四十になる私とでは
時間の密度は違えども
今日はどちらにとっても
やがて忘れられる一日なのだろう
と言い聞かせるように私はそこにいる
せめてと娘の姿を焼きつけようとするが
そのことさえも日常の中に紛れ込んでしまう
雨に濡れた妻が
その時なにをしていたのかさえ
もうこの詩の中に存在していない
二〇一六年一〇月一〇日(月)