

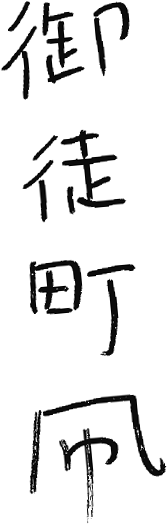

二〇〇九年〇三月一六日(月)
ダイニングには母さんはいなくって、空のスープ皿と白パンとミルクの瓶がテーブルの上に置かれていた。
空のお皿は窓の向こうから差す太陽の光に反射してキラリと輝いてはぼくの視線を刺激した。
母さんは洗濯物かなにかの用で洗面所のほうにいるのだろうと思い、ぼくはお皿にスープをよそって、一人でブレックファーストをすませることにして、椅子に座るタイミングと同じくしておもむろにパンにかじりついた。
奥歯の痛みはさっきよりひいていて、パンを噛みながら、スープを木のサジですくい口に運んだ。
ダイニングにある大窓から裏の山々へとつづく道が見え、その道の先の木々が重なるあたりに視線を合わせながら、メンペイムのことをぼくは考えていたのだと思う。
スープとパンの味が口の中で混ざり合うのを感じていると、廊下の向こうから母さんの足音が聞こえてきた。
「遅れないようにねー」と母さんは言っているけど、その響きの中に目的語を感じることができなくて、そのことになぜかぼくは優しい気持ちになれたのだけれど、それはきっとぼくの中にある幼心が反応しただけのような気がして、すぐに返事ができなかった。
母さんがダイニングに入ってきて、あれいたの? というような表情をしたことで、さっき母さんはまだ庭にいるであろうぼくに話しかけていたことをぼくは感じて、「うん」とかなり遅めのタイミングでさっきの返事に“もう食べてるよ”という“いただきます”的な意味の相づちを一つにして打って、口の中のものを胃に流し込み、リズムを整えるようにミルクに一口だけ口をつけた。
母さんはぼくを見ることをせずに「はーい」と長めの返事をして、手に持っていた洗濯籠を揺さぶるように大股で庭へ歩いていった。
再び一人になったダイニングで、ぼくはパンを手にしたまま、山の上にかかる雲を見ていた。
二〇〇九年〇三月一六日(月)
